こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。
ついに消費税アップしましたね。缶詰とか日持ちのいいものを買いだめしとこうと、頭の中ではいつも思っていたのですが、バタバタしてるうちに結局買わずじまいで4月を迎えてしまいました。
税金というと、今日は抵当権と国税の優劣について相談を受けたのでブログにしたいと思います。
1、1番抵当権に優先する見えない敵
お金を貸す人が借りる人の不動産に抵当権を設定する場合、登記簿を見て先順位の抵当権登記があるかどうかを調査します。
では、先順位の抵当権がなければ、必ず1番の順位を確保できるのでしょうか。
これについては絶対そうとはいえません。
なぜなら、借りる人が国税を滞納している可能性もあるからです。
国税徴収法8条によると
「国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。」
とあります。
つまり国税最強というのが日本の債権ルールの大原則なのです。
これが「見えない抵当権」と呼ばれるものです(抵当権ではないので比喩ですが)
他の抵当権は登記簿を見ればわかるので「見える抵当権」です。そのため登記簿の閲覧により簡単に調査することができます。
それに対して、「見えない抵当権」の調査は難しいですよね。調べようと思えば調べる事ができなくもないのでしょうが大変です。
たとえば、借りる人に所得税の滞納がないかを調べるためには、事前に支払済の数年分の領収書を提示してもらうという方法もあるかもしれません。しかしそこまでするのもどうかと思いますし、仮に見せてもらっても国税はそれだけじゃないですからね。相続税の未払いだってあるかもしれません。
そのため1番順位の抵当権で登記したとしても、ある程度のリスクは残るということになります。
2、見えない抵当権に優先する場合
それでは、抵当権は絶対に国税に勝てないのでしょうか。
実は国税徴収法16条に以下のような規定があります。
「納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。」
この規定によると「法定納期限等」より前に抵当権の設定登記をすれば、国という最強のラスボスにも勝てるという事になります。
法定納期限は個人の所得税の確定申告の場合、毎年3月15日くらいです。
そうすると、3月15日を過ぎた後に抵当権の登記を入れても絶対に国税には勝てないのでしょうか。
ここで気になるのは16条が、「法定納期限」ではなく「法定納期限等」というように「等」をちょこんと付け加えており、後者の方が前者より広い概念である事がわかります。
この「法定納期限等」の定義は国税徴収法15条1項にあります。
「納税者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。)以前に設定されているものであるときは、その国税は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。」
「各号に定める日」とあるので、たとえば1号を見ると
「法定納期限後にその納付すべき額が確定した国税(過怠税を含む。)
その更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日(申告納税方式による国税で申告により確定したものについては、その申告があつた日)」
とあります。
この1号の具体例としては修正申告があります。
たとえば、売上漏れがあって5月20日に300万円の所得税アップとなる修正申告をしたとします。その場合の法定納期限等は、原則の3月15日ではなく、修正申告した日の5月20日になるわけです。
そうすると3月15日の段階では、発生していないと思われてた未申告分の所得税300万円が5月20日に一気に顕在化するわけです。
この300万円については、見えないどころか、「全く見えない抵当権」です。
少なくとも3月15日の確定申告で発生する所得税は予測もある程度たてる事ができます。借りる人の商売がうまくいってないから、もしかしたら所得税未払いじゃないかとか。
しかし、売上や経費をごまかしてた場合に、あとで調査が入って修正申告をするといった事はさすがに抵当権者にとって予測不可能です。
そのため、こういった予測不可能な事情はさすがにそのような事情があったとき(修正申告等)をもって、「法定納期限等」とする事で、担保を取ろうとする者に一定の譲歩をしたのでしょう。
国税怖いですね。これだけ強大な権限が与えられてたくさん税金とってるんですから、ちゃんと正しく使ってもらいたいものですね。

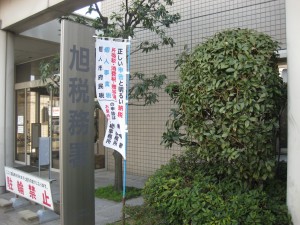 こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。
こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。