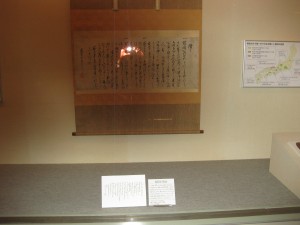こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。
最近、ご家族に内緒で業者に過払いの請求をしたいとのご依頼がありました。
この点については、極力ばれないようにするものの、絶対に秘密を保証することはできない事を依頼者の皆さまに事前にご了解いただいた上で手続きを進めるようにしています。
なぜなら、過払い訴訟を起こした場合、逆に原告相手に調停を起こしてくるような業者があり(アイフルとか)そのような場合ご自宅の住所に調停申立書が届いたりするケースがあるからです(もちろんこのような半ば嫌がらせをしてくる業者に対しては慰謝料の請求も含めて毅然とした対応をする必要がありますが)
それともうひとつ業者が第一審で敗訴した後に控訴した場合も問題が生じえます。民事訴訟法289条は控訴状は、「被控訴人」に送達しなければならないとしているところ、同103条は送達場所について送達を受けるべきものの住所等としているため、控訴条が原告の住所に届く可能性があるからです。
この点、裁判所によっては申請すれば第一審の代理人の事務所へ控訴状を送達するという運用をしてくれる事もあるようです。
しかし、これは事実上そのように運用しているというだけであって、被控訴人にとって送達方法の選択権を法的な権利として認めているわけではありません(同104条1項により住所と異なる送達場所を裁判所に届ける事ができますが、控訴審が係属する前でもこのような届出が認められてるわけではないように思います)。
この点は、被控訴人に送達方法を選択させる権利(たとえば裁判所に控訴状を取りに行くとか)を認めるように法改正をしていただきたいところです。
そもそも、これだけ個人情報の取り扱いが声高にさけばれている中、重要なプライバシーを含む裁判書類について自宅に届ける事を原則とする民事訴訟法の規定はいかがなものでしょうか。
確かに、同条の規定は、控訴状をしっかり被控訴人に送達する事で、同人に控訴審を争わせる機会を保証するものであり、その立法趣旨はわかります。
しかし、わざわざ自宅に送らなくても被控訴人が裁判所に控訴状を取りにいくという方法でもいいはずです。運転免許証等の身分証明書を提示した形での受け取りにすれば裁判所が第三者に控訴状を渡してしまうというリスクも発生しません。
裁判所としても、控訴状を郵送する手間が省けるという合理性もあります。
確かに第一審の訴状の場合は裁判所が被告の連絡先として住所しか把握していない場合もあり、そのような場合は訴状を郵送するよりほかないでしょう。
しかし控訴の場合は別論です。
なぜなら前提として第一審が行われているからです。その場で原告や被告、その代理人といくらでも控訴後の連絡手段を打ち合わせてしておく事はできるはずです。
そのため、下記のような条項を送達の条項に盛り込む事が検討されていいのではないでしょうか。
「裁判所は被控訴人に対して、控訴状の送達をする場合、第一審において当事者から携帯電話等による通信機器による連絡を希望する旨の申告がある場合、同連絡先にその送達方法についての確認の連絡をしなければならない。ただし同連絡先へ連絡をしたにも関わらず被控訴人が3日以内になんらの回答もしない場合は、同人の住所へ控訴状を送達することができるものとする。」
上記のような改正がされれば、まずは裁判所は被控訴人の携帯へ連絡する義務が生じますし、もし同人が裁判所からの電話を無視すれば、そのときはじめて控訴状を自宅へ送ることで訴訟の遅滞も防ぐ事ができます。
このような形で控訴状の受取方法について被控訴人に選択権を認めるのが個人情報保護法やプライバシーの理念に合致します。
そもそも裁判を受ける権利は憲法32条で認められているものです。このような憲法上の権利が、ご家族に知られる事を回避するため、事実上制限を受けるというのはよろしくないのではないでしょうか。
徹底的な個人情報保護で、国民が裁判に不安を持たずに権利行使できるようになることが望まれます。